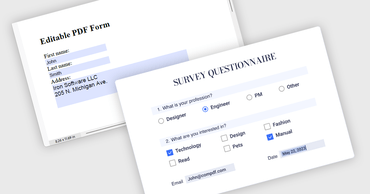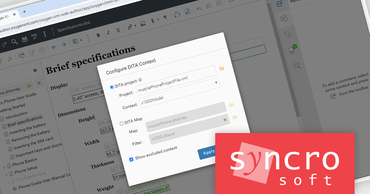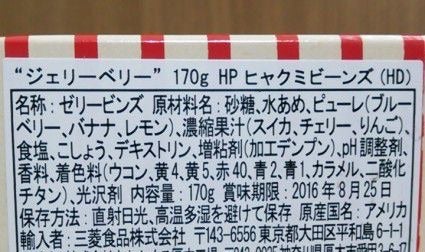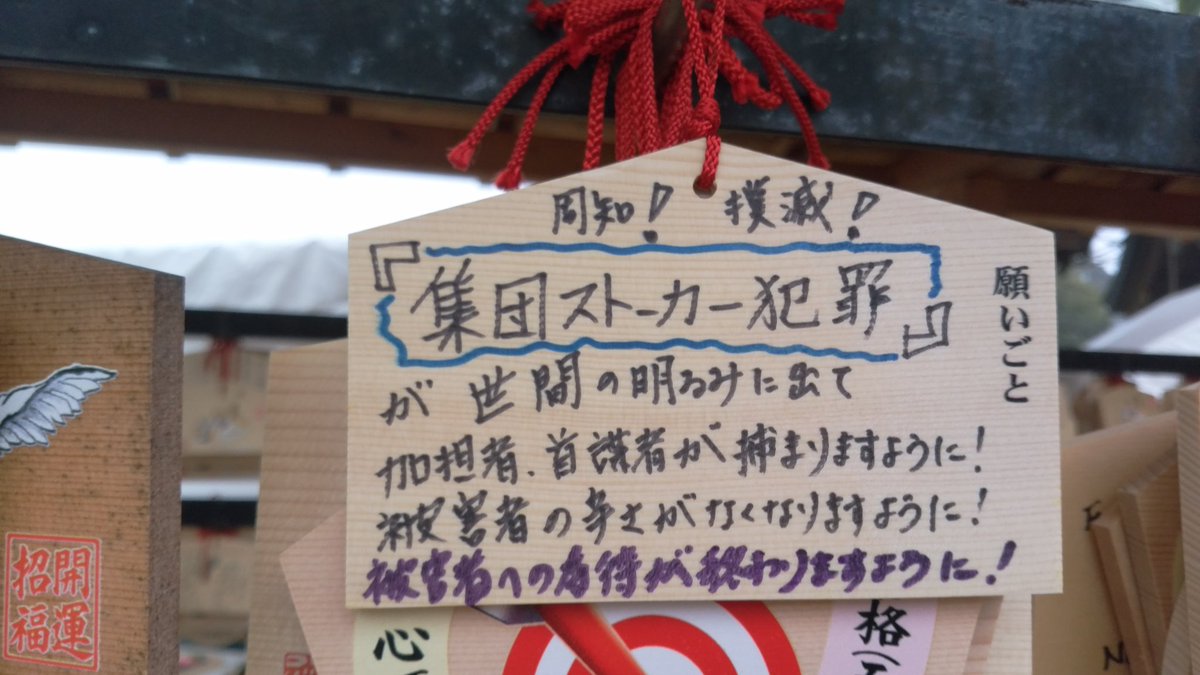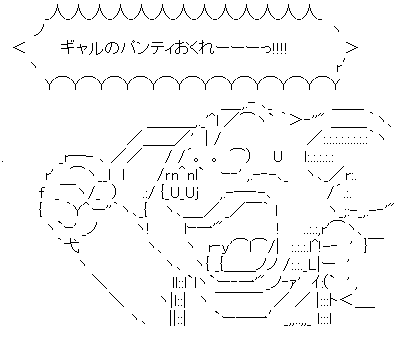ジェンダーについて話しているとき、最も残念なのは次の論法でくる女性だ。
ジェンダーについて話しているとき、最も残念なのは次の論法でくる女性だ。
1. 私は女である
2. 故に正しい
3. 従って議論は私が裁定する(できる)
彼女に言わせると、「私の意見=女一般論」なので「ジェンダー論=女一般論が正義」⇒「ジェンダー論=私の意見が正義」という図式が成り立っている(女性複数の場合は、それぞれ全てが正しい)。すると男どもは黙ってひれ伏して謹聴するしかない。
だが、次の瞬間に気づく、これは、まさに男どもが何百年もやってきたことを、そのまま逆にした構図だ。だから「女ゆえに私こそ正義」を吹聴する彼女ばかりを責めることはできない。せめてもう少しエビデンスベースで学べないかと思っていたら、良さそうなブックリストがあった。「フェミニストとしてすすめる、フェミニズムに関心を持つための本」というリストで、以下の通りにまとめてある。
(1) 物語・ノンフィクション編
(2) 理論・学術・専門書編
(3) 批評編
アトウッドやイプセンといった文学寄りには馴染みがあるものの、学術書や批評は、ほとんど知らない興味深いラインナップなり。「面白そう」と言ったら叱られそうだが、タイトルに最も惹かれた一冊がこ『母性という神話』だ。原題は"L'Amour En Plus"(後から付け加わった愛)で、日本語のお題はタイトル詐欺になっている。
たとえば、辞書で「母性」を引くとこうある。
女性がもっているとされている、母親としての本能や性質。また、母親として子を生み育てる機能。
(大辞林 第三版)
この「母性」と「本能」の緊密な結びつきに異議申し立てをしたのが、本書になる。「母性愛」とは本能ではなく、子どもとの触れ合いの中で育まれる愛情であり、これを「本能」とするのは、父権社会のイデオロギーであり、近代が生み出した神話に過ぎないことを証明している。
著者は、17世紀から18世紀のフランスの都市部で、子どもを乳母に預けることが流行したことを引きながら、いかに母親は子どもに無関心だったかを述べる。そして、運よく幼児期を生き延びたとしても、寄宿学校や修道院へ厄介払いされていた実情を示す。もし母性本能が女にとって本質的で普遍性があるのなら、いかなる時代のどんな母親も、この愛を実現していたはずである。従って乳母の事例は、反証になるというのだ。
この「母性本能」は何なのかというと、イデオロギーだという。ここは非常に誤解を招きやすい箇所で、事実、新版の序文で「母性愛は18世紀の発明だとはけっして書いていない」と断っている。母性愛はどの時代にも見られるが、他の感情と同様で、現れたり消えたりする不安定なものだという。しかし、「母性愛」が、女性の本性として扱われ、「母性愛=本能」という図式が常識として扱われていることが、間違っているというのだ。日本語タイトルは、『母性本能という神話』とすべきだろう。
では、「母性愛=本能」という図式がどのように作られたか。著者は、ルソーやフロイトを用いて、女性を母親の役割に押し込める構図を描き出す。それは、こんな図式だ。女は母親に、それも「良い母親」になるために生まれてくるのである。いつも家の中にいて、子どもの栄養と衛生に気を配り、献身的で優しい母であるべき―――という構図だ。
そして、これに違和感を抱いたり、逸脱しようものなら「病的」「異常」のレッテルを貼り付け、不安や罪悪感を煽り立てる。これは、現代にも連なっている。『ひよこクラブ』の相談室で、「どうしても子どもに愛情がもてない、私は異常なのだろうか」という悩みを見たことがあるが、その裏に「母性愛=本能」という神話が刷り込まれている。
「子どもを産むこと」は確かに女にしかできないが、だからといって「子どもを愛すること」は女に押し付けるのは、確かにおかしい。「母性本能」は言葉としてあるけれど、「父性本能」は無い。この欺瞞に気づけただけでも、本書の意義は大きい。わたし自身、子どもに抱く愛情は、フルパワーで費やした育児の日々を通じて大きくなり、毎日の生活の中でアップデートされる感情だ。そういう意味で、この愛は、"L'Amour En Plus"(後から付け加わった愛)なのだろう。